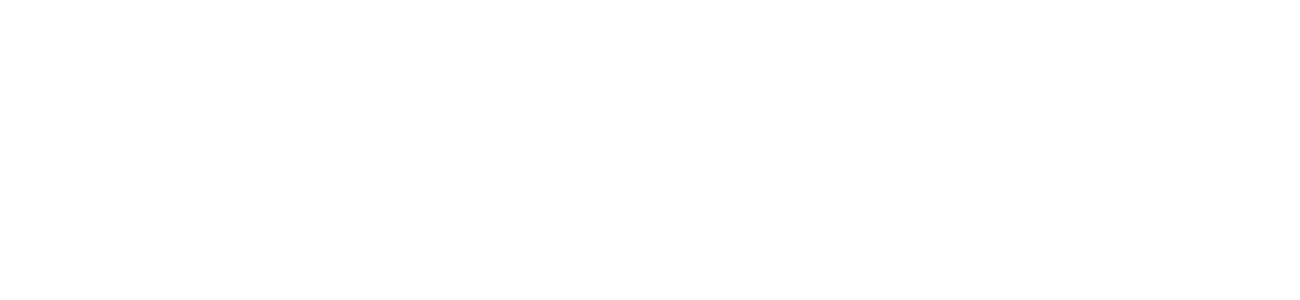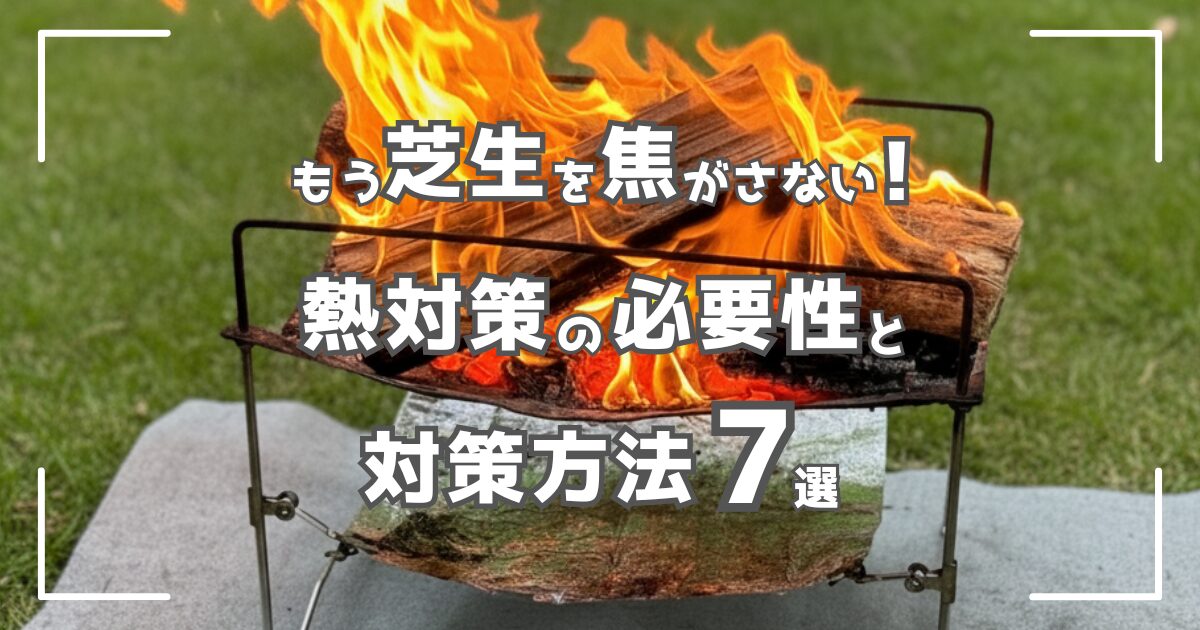キャンプで焚き火をする時間は、日常では味わえない癒やしのひとときですよね。
ですが、綺麗な芝生サイトなどで焚き火をする際、焚き火の熱で芝生を焦がしてしまわないか不安に感じたことはありませんか?
キャンプを始めた頃は特に不安で、ちらちら確認しながら焚き火していました。
万が一、芝生を焦がしてしまうと次の利用者が気持ちよく利用できなかったり、そのキャンプ場で焚き火が禁止になってしまったり、最悪の場合山火事に発展する可能性もあります。
一般的な対策として、焚き火台を使い分けたり、火床の下に薪を並べたりする方法もありますが、それらよりも手軽で効果的だと個人的に感じているのが、アルミホイルを活用する方法です。
この記事では、焚き火の熱対策の必要性や芝生が焦げる原因を解説した後、7つの熱対策方法を200泊以上欠かさず焚き火をしてきた経験を元にご紹介します。
この記事で分かること
- 芝生を焦がしてはいけない理由
- 焚き火で芝生が焦げる原因
- 7つの焚き火の熱対策方法
色々な熱対策方法を知っておけば、今後焚き火で芝生を焦がしてしまう不安を感じることなく焚き火を楽しめるようになるので、熱対策に不安がある方はぜひ参考にしてみてください!
そもそもなぜ芝生を焦がしてはいけない?
芝生を焦がしてはいけない理由は主に「山火事の原因になる」「芝生が枯れてしまう」「焚き火が禁止になってしまう」の3つが挙げられます。
芝生を焦がしてはいけない理由
- 山火事の原因になる
- 芝生が枯れてしまう
- 焚き火禁止になってしまう可能性も
それぞれ詳しく解説していきます。
山火事の原因になる


特に秋冬の乾燥した時期には、芝生についた火が延焼し山火事に繋がる可能性があります。
トイレ等で少し目を離した隙に芝生に火がつき、戻ってきたときには燃え広がっていた、ということも十分に考えられます。
どのくらい燃え広がりやすいかは下記動画が分かりやすかったので、気になる方は観てみてください。
思っている以上に燃え広がるので注意!
芝生が枯れてしまう


庭を芝生が侵食していく様を見ながら育ったので個人的には意外だったのですが、芝生は非常にデリケートな植物です。
見た目で焦げていなかったとしても、40~50℃程度の熱がじんわり長時間続くだけでも細胞が死んでしまい、芝生が根っこから枯れてしまうこともあります。
しかし、地面に生えた芝や植物などは40〜50度の温度に長時間晒されると細胞が死ぬと言われています。
引用元:【キャンパー必見!!】正しい焚き火で綺麗な地面を維持しよう! – ZEN Camps
焚き火の熱だけでなく、お湯やジュースなどの塩分・糖分を多く含む液体でも枯れてしまうことがあります。
また、車や人が踏みつけることもダメージに繋がることもあります。
芝生を焦がさないだけではなく、熱を伝えない工夫も必要です!
焚き火禁止になってしまう可能性も


根っこまで枯れてしまった芝生は自然に元に戻るまで数ヶ月〜1年、最悪の場合回復しない場合もあります。
そのため、芝生を焦がす利用者が多ければ焦げ跡だらけのキャンプ場になってしまいます。
芝生はただでさえメンテナンスコストがかかるのに、それに加えて何度も修繕するとなると、キャンプ場が焚き火を禁止する選択をせざるを得なくなる可能性もあります。
直火ができるキャンプ場が減っているように、芝生の上では焚き火禁止のキャンプ場が増えてもおかしくはないと思います。
焚き火で芝生が焦げる原因
実際に芝生を焦がさないための対策方法を解説する前に、そもそもなぜ焚き火台、焚き火シートを使っているのに芝生が焦げてしまうのかを解説します。
結論から言うと、焚き火で芝生が焦げる原因は「焚き火台からの輻射熱」と「焚き火台から落ちた熾火」の2つが主に挙げられます。
芝生が焦げる原因
- 焚き火台からの輻射熱
- 焚き火台から落ちた薪や熾火
2つ目に関しては感覚的に理解できると思いますが、1つ目の「輻射熱」は目に見えないのできちんと対策しておかないとうっかり芝生を焦がしてしまう原因になり得ます。
以降でそれぞれの原因について詳しく解説していきます。
焚き火台からの輻射熱


芝生が焦げる原因のほとんどは焚き火台に溜まった熾火(おきび)から発生する輻射熱です。
熾火は基本的に炎が上がっていないのであまり熱そうに見えないですが、実はこの熾火の温度は約400~800℃に達します。
焚き火で燃え上がっている炎はおおよそ1000℃前後なので、温度はそれほど変わりません。
この高温に近距離かつ長時間さらされることにより、芝生が焦げてしまいます。
焚き火台から落ちた薪や熾火


芝生が焦げるもう1つの原因は焚き火台から落ちた薪や熾火です。
熾火は長時間・安定的に燃え続ける性質があるので、焚き火台から落ちたとしても数百℃の温度を保ったまましばらく燃え続けます。
そのため、熾火が芝生の上に落ちたまま放置してしてしまうと芝生が焦げるのはもちろん、地中にまで熱が伝わり芝生が根から枯れてしまうこともあります。
輻射熱に比べて影響範囲は小さいものの、薪が長い場合や小型の焚き火台を使用しているときには注意が必要です。
芝生を焦がさないための7つの熱対策
ここからは実際にどうやって熱対策をすればいいのかについて解説していきます!
芝生を焦がさないための熱対策は以下の7つです。
芝生を焦がさないための7つの熱対策
- 大きめの焚き火シートを使う
- 焚き火台の下に薪を並べる
- 火床が高めの焚き火台を使う
- メッシュの焚き火台は避ける
- 焚き火台を台に乗せる
- アルミホイルで遮熱する
- 焚き火専用の熱対策ギアを使う
どれか1つをやれば十分ということは基本的に無いので、2つ以上組み合わせて対策することをおすすめします。
それではそれぞれの対策について詳しく解説していきます!
1. 大きめの焚き火シートを使う


最も簡単でどんな焚き火台でもできる対策は、大きめの焚き火シートを使うことです。
焚き火台に対して余裕を持たせたシートを敷くことで、燃えかかった薪や熾火が芝生に直接落ちるのを防げます。
灰や炭の破片も焚き火シートの上にとどまってくれるので片付けも楽になります!
ただ、一般的な焚き火シートは難燃性・耐熱性はあっても遮熱性はほとんど無いので、この方法では輻射熱対策としてはあまり効果がありません。
2. 焚き火台の下に薪を並べる


焚き火台の下に余った薪を並べる方法も薪の乾燥をしつつ、熱対策もできるので一石二鳥でおすすめです!
この方法は火床が低いとできないのと、火床が近いと並べた薪が燃えることがあるので、しっかり見ている必要があります。
3. 火床が高めの焚き火台を使う


3つ目はそもそも火床が高めの焚き火台を使用する方法です。
火床の高さを確保することで、輻射熱を軽減できるため熱対策として有効です。
熱対策の観点では火床の高さは最低20cmくらいは必要かなと思います。
もちろん焚き火台や燃やし方よって必要な高さは異なります!
4. メッシュの焚き火台は避ける


火床の素材も重要で、メッシュタイプの焚き火台は避けるのが無難です。
金属板タイプのものに比べてメッシュタイプの焚き火台は熱が下に伝わりやすいです。
メッシュタイプの焚き火台のレビューでよく「ピザが焼ける!」と言われるのはそのためです。
他に焚き火台を持っていない場合やどうしてもメッシュタイプの焚き火台を使用したい場合は、後述するアルミホイルによる熱対策などを併用することを強くおすすめします。
5. 焚き火台を台に乗せる


5つ目は焚き火台を台に載せて物理的に地面から離す方法です。
3つ目にご紹介した火床の高い焚き火台を使用する方法と同じく、地面との距離を取ることで輻射熱を影響を抑えられます。
キャンプ場によっては木の台やブロックが用意されていることもあります!
焚き火の最中に足が畳まれてしまわないように注意は必要ですが、ウッドストーブやコンパクトな焚き火台なら100均の焼き網スタンドを台として使用するのがおすすめです!
6. アルミホイルで遮熱する


6つ目は個人的に最も手軽で効果を感じているアルミホイルで遮熱する方法です。
使うアルミホイルは普通のアルミホイルで問題ありません。
焚き火台のサイズに合わせてアルミホイルを最低でも3回以上折り重ね、四隅にクリップをつけるだけで作れます。
四隅のクリップで焚き火台の脚に固定することで、焚き火台からの熱はしっかり反射しつつ、アルミホイルと芝生との間は空気が流れるので、温度上昇を防げます。
アルミホイルの下に手を入れても全く温かさを感じないくらいの効果があります!
焚き火シートの上に直接置くだけでもある程度効果はあるのでアルミホイルだけでもあると良いです。


7. 焚き火専用の熱対策ギアを使う
焚き火専用の熱対策ギアを使うのも一つの手です。
市販されている製品はそう多くはありませんが、効果的なものもあります。
例えば、ZEN Campsでは表面にアルミ加工が施された焚き火シートを、Tokyo Campでは焚き火台スタンドを販売しています。
まとめ:焚き火の熱対策をして芝生を焦がさないようにしよう!
今回は、焚き火の熱対策について解説しました。
焚き火台からの輻射熱や落ちた熾火は、気づかないうちに芝生を傷つけてしまいます。
大切な芝生サイトを守り、他の利用者への配慮や、キャンプ場での焚き火禁止といった最悪の事態を防ぐためにも、熱対策はキャンパー必須のマナーと言えます。
焚き火シートや遮熱ギアの活用、アルミホイルでの代用など、本記事で紹介した対策方法から複数を組み合わせて実践することが重要です。
万全の対策で地面へのダメージを防ぎ、マナーを守って焚き火を楽しみましょう!
質問や感想、ご指摘などありましたら、記事下のコメントからぜひ気軽に教えてください!